
 |
|
|
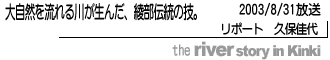 |
![]()
|
||
伊佐津川に来た。由良川水系ではなく独立した川だ。綾部市が源流で、北隣りの舞鶴市を通って舞鶴西港に注ぐ。由良川は一級河川だが、この伊佐津川は二級河川。この違いには、水質も川の優劣もない。一級河川は、国土保全上または国民経済上、つまり治水と利水の面で、とくに重要と国土交通大臣が指定した川だ。一級河川は国が管理し、二級河川は都道府県が管理する。ただ、一級河川は、国が直接管理する部分と国から委任されて都道府県が管理する部分とがある。伊佐津川のように京都府だけを流れる川と違い、由良川のように複数の都道府県(京都府・兵庫県)を流れる川は、一つの都道府県では管理できない。逆に、複数にまたがっていない川でも、治水上または利水上とくに重要な場合は一級河川になる。 |
||
|
|
||
 「約800年前、平家の落人(おちうど)が住み着き、山ばかりで耕地がないため、生活の糧として紙すきを始めたのが黒谷和紙と伝えられています。そのころは『小判』という小さい紙をすいていた程度で、農家へ行っては米や豆と交換して生活をしのいでいたようです」 「約800年前、平家の落人(おちうど)が住み着き、山ばかりで耕地がないため、生活の糧として紙すきを始めたのが黒谷和紙と伝えられています。そのころは『小判』という小さい紙をすいていた程度で、農家へ行っては米や豆と交換して生活をしのいでいたようです」 |
||
会館の前にコウゾ、ガンピなどの木が植えられている。 |
||
|
|
||
黒谷和紙会館 ■開館時間/平日=8:30〜17:00 第2・4土曜日と 第1・3・5日曜日=9:00〜16:00 第1・3・5土曜日=9:30〜12:00 ■休館日/第2・4日曜日 ■TEL/0773-44-0213 |
||
|
|
||
綾部市で、由良川の綾部山家観光やな漁、「黒谷川」の水を使う黒谷和紙の話を伺った。水を操る紙すきの技を見て、遊ぶだけではない、違う形での川との触れあいを見た気がした。やな漁、黒谷和紙、その伝統を知ってほしい |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||