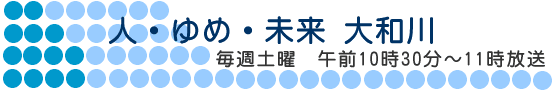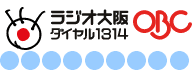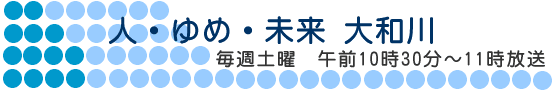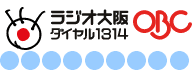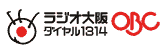| 飛鳥川に残る歌の謎
 月読橋
月読橋 |
飛鳥川に架かる美しい月読橋。そこに立ち、まずは大阪の飛鳥川について伺いました。
高野 飛鳥川は東に見える美しい二上山のふもと、ここから5〜6kmほど行った竹内峠辺りを源流に、羽曳野市の東部を西へ流れ、ここから1kmほど下った所で石川に合流します。この辺りで幅20mほどの小さな、そして、短い川です。飛鳥と聞くと奈良を思い浮かべる方も多いのですが、実は全国に20カ所近くあるようです。羽曳野市にもあって、日本書紀や古事記などに出てくる「遠(とお)つ飛鳥」「近(ちか)つ飛鳥」という言葉は、難波(大阪)から見て遠い奈良を遠つ飛鳥、近いこの地を近つ飛鳥と呼んでいるものと、一般的には考えられています。
月読橋から20〜30mほど。立派な歌碑があります。
高野 高さが2mほどある立派なこの石碑は、文化2(1805)年に建てられた非常に古いものです。
あすか河 もみち葉なかる 葛城の
山のあき風 吹きそしぬらし 人麿
刻まれているこの歌は、飛鳥川にモミジが流れている、ここから見える葛城山に秋風が吹いているんだ、という意味に取れます。直接的で分かりやすい。
この場所で詠んだ歌として、しっくりきます。
高野 ところが、これには元歌があり、人麿はそれをアレンジして作ったんです。それを「本歌取り」と言いますが、元はこんな歌です。
明日香川 もみち葉流る 葛城の
山の木の葉は 今し散るらし
 人麿の歌を刻んだ歌碑
人麿の歌を刻んだ歌碑 |
こちらは「山の木の葉は今しちるらし」とし、「葛城の山の木の葉が、今、散ってるんだろうな」という意味になり、微妙な違いが出てきます。遠くの葛城山を思い浮かべて詠んだ歌とも取れるわけです。万葉集には、奈良の飛鳥川を詠んだ歌はたくさんありますが、河内の飛鳥川の歌はこれ以外にありません。そのことからも、河内の飛鳥川の歌だという解釈に異論を唱える人がいて、二つの考え方が存在するのです。
|
神社に残る石の謎
 杜本神社
杜本神社 |
月読橋から徒歩5分ほど、杜本(もりもと)神社にやってきました。川沿いではありませんが、竹林が風にそよぎ、ウグイスが鳴く雰囲気満点の神社です。
高野 今から200年ほど前の僧侶・覚峰(かくほう)がここ駒ケ谷にやってきて、かなり荒れていた金剛輪寺に入り、立派に建て直しをしました。彼は、国史や和歌、また、オランダの測量法などの西洋学問を勉強し、一度すたれた1弦の琴を復活させるなど、多芸多才の僧侶で、先程の歌碑や神社入り口の石灯ろうの文字も、彼の筆によるものです。
拝殿の裏手にも、覚峰ゆかりの石があります。高さは1mぐらいでしょうか。
高野 左右で1対になっているこの「隼人(はやと)石」には、
頭がネズミで体が人間という、不思議な絵が描かれています。実はこれによく似た石が、奈良市の「聖武天皇皇太子那富山(なほやま)墓」にもあり、この隼人石も古代に造られたものと考える説がありました。
奈良の石は御陵を囲むように立ち、全部は残っていませんが、十二支が刻まれていたらしい。それぞれの方角の神様により、御陵を守る意味があったようなのです。
ところが、この隼人石は古代に造られたものではないとのこと。
高野 江戸時代に覚峰が奈良の石を真似て造ったのだろうと、今は考えられています。その奈良の像とこの像かぴったり重なるため、おそらく、拓本でも手に入れ、それを元に造ったのではないと思われます。
 丘の上からの眺め
丘の上からの眺め |
最後に、河内飛鳥を見渡せる丘に上がりました。飛鳥川の源流や竹内峠、葛城山も見渡せます。
高野 ここからは丘に囲まれた飛鳥川流域が見渡せ、それが周囲から切り離された別世界みたいに見えないでしょうか。所々に、家並みや池、学校があり、田畑が広がっている。箱庭を見えます。また、あそこの森は聖徳太子の墓、さらに向こうの森は推古天皇の御陵というように、歴史を語るものがこの飛鳥川周辺にはたくさん残っています。
******
 高野さん
高野さん |
羽曳野市を流れる飛鳥川を訪ね、歴史散歩を楽しみました。歴史にあまり詳しくない私も、お話を聞きながら歩いているうち、段々と興味がわいてきました。これから暖かくなり、ますます見どころも増えていきます。皆さんも、ぜひ一度お出かけください。次回訪ねる、もう一つの飛鳥川も楽しみです。 |