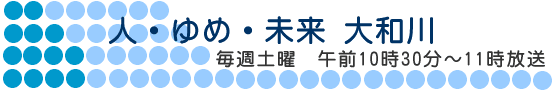
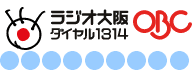
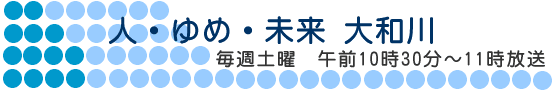 |
|
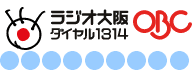 |
地域の人に愛され 山に囲まれた奈良県桜井市針道地区。雪が少し残り、幅2mほどの針道川には底が透き通って見えるほど澄んだ水が流れています。この水は、寺川を経由して大和川へと流れ込んでいます。今日は、ここで年に1度の「綱かけさん」が行われ、巨大なしめ縄のようなものが針道川に架けられます。一体、どんな綱なのでしょう。まずは、ここから1kmほど上流にある公民館に行き、綱作りを見ることにします。 |
| 欠かさず行われてきた伝統行事
針道公民館には二本のはしごが掛けられ、その中段に1人が立ち、下で編む2人とわらを渡す1人の計4人が、2組で綱を作っています。針道地区の区長、東谷育宏さんにお話を伺いました。 公民館の中では長老2人がシキビ(仏前草)を用意していて、色々な作業が同時に行われています。 綱かけには、どういう意味があるのでしょう。 世話役は針道区長が務めるのでしょうか。
針道地区の入り口に戻りました。運ばれた2本の綱は、針道川と横の細い道をまたいで架けられます。下流に向いて左側のケヤキと右側のカシノキに付けられますが、最初に2本の綱をつないだ後、川を渡って姉を、山を少し登って妹をくくり付けます。架けた後には、カシノキの前で、巻物を広げ、般若心経を読んでお祈りの行事をします。 |
木に古い綱の一部が残っています。年の途中で朽ちて落ちてしまうようです。 新たに架かった綱を見て、どう感じるのでしょう。 綱かけを一生懸命守りつづけ、針道川をとても大切にしている皆さんのお陰で、水もすごく奇麗です。 針道生まれの新谷善範さんにも伺いました。 この水が流れる大和川の下流でも、多くの方が奇麗にしようと色々な活動をされています。
******
1月11日行われた桜井市針道地区の「綱かけさん」を取材しました。奈良県では、このような「勧請(かんじょう)綱かけ」行事がまだ残ってはいるものの、やはり段々と減っています。そんな中、皆さんが仲良く団結して作業している様子を見て、こうした行事の大切さを感じます。また、少しうらやましくも思いました。 |
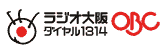 |