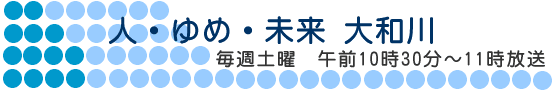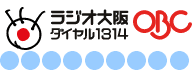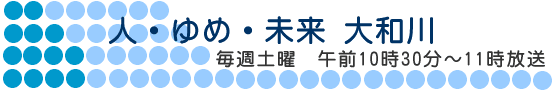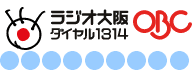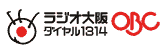| 支流ごとにきめ細かく水質改善
まずは奈良県河川課の中川保さんに、「大和川清流復活ネットワーク」の設立趣旨を伺いました。
中川 大和川の水質は良くなっているものの、まだ環境基準をクリアできず、3年連続水質ワースト1のため、支流ごとに問題点を洗い出して戦略的に水質改善に取り組もうと設立しました。以前からの担当である河川課、環境政策課、下水道課に加え、農業での化学肥料使用や畜産によるし尿処理で川と関係する農林部や、企業の排水関係を担当している商工労働部も参加。また、国と県内市町村、さらに、オブザーバーとして3市民団体も参加しています。
昨年11月18日に開催された初会合では、どのようなことが話し合われたのでしょう。
中川 これまでの水質改善の取り組み体制や、水質指標であるBOD(生物化学的酸素要求量)の変化、大和川に対する県民のイメージ、大和川と国内外の川との比較、水質の悪い国内河川での取り組みなどについて話し合いました。
これまでの取り組み体制は、どのようなものたったのでしょう。
中川 奈良県と大阪府、流域自治体などが、昭和42年に「大和川水質汚濁防止連絡協議会」を設立し、油の流出など水質事故への対応を始め、平成5年には水質改善を扱う本格的な組織「大和川清流ルネッサンス協議会」を設置。さらに、平成17年には性格の違うそれらが合わさり、国、奈良県、大阪府、36市町村が参加する「大和川水環境協議会」が出来ました。
今後すべきことも話し合われたとのこと。
中川 組織横断的な取り組みをすること。流域の実情を知り、情報提供して水質改善の必要性を県民と共有していくこと。3年以内にワースト1から脱却するなどの目標を設定すること。支流ごとにきめ細かな水質改善計画を立てることが話し合われました。そのためには、支流や市町村ごとの下水道普及率や合併浄化槽の設置状況を明らかにすることが必要だと思います。
下水の普及と合併浄化槽で水質改善
今度は下水道と水質の関係について、下水道課の東川(とがわ)昌司さんに伺いました。
東川 大和川のBOD平均値を見ると、下水道普及率が13%だった昭和53年には1リットルあたり19.7mg、75%となった平成19年には4.7mgでした。
|
下水道普及率とは、どういうものなのでしょう。
東川 下水道には普及率と接続率(水洗化率)があり、普及率は下水道の本管が家の前にまで整備された率であり、行政の仕事です。接続率は各家庭が生活排水を下水管に流す工事をしている率で、これを上げることが最も重要です。そのために、流域下水道センターをキーステーションに啓発活動を行っていますが、今後はそれを一層充実させていきます。
技術的な工夫も行っていくとのこと。
東川 奈良県における大和川の浄化センターは毎秒約20万立方メートルの下水処理水を放流していて、大和川の水量の5割〜6割を占めているため、放流水の水質を良くすることが全体の水質改善につながります。しかし、高度処理には多額の設備費が掛かるため、現在の設備で水質の向上に取り組んでいこうと考えております。
続いて、環境政策課の辨天(べんてん)繁和さんにお話を伺いました。
辨天 浄化槽には、トイレの水だけが処理され、台所や洗濯などの生活排水がそのまま川に流れる単独浄化槽と、全て処理される合併浄化槽があります。単独浄化槽だと汚れた有機物の約8割が残りますが、合併浄化槽ではその8分の1にまで処理されます。単独浄化槽は平成13年以降、設置できなくなりましたが、大和川にはそれ以前のものがまだ多数残っており、くみ取り式排水と合わせ、汚濁原因になっています。
それを合併浄化槽に換えていくことが大事です。
辨天 奈良県内では流域23市町村のほとんどが下水道処理区域ですが、下水道が及ばない地域では8市町村で補助制度を設け、設置費用の約4割を国と県、市町村で補助し、合併浄化槽の設置を進めています。
******

左から 辨天さん
東川さん 中川さん
|
大和川清流復活ネットワークにオブザーバー参加している市民団体は、現在のところ、「大和川市民ネットワーク」「大和川循環型社会創造機構」「エコフォーラム21」の三つ。中川さんによると、これから多くの方に声を掛け、一緒に啓発活動をしていくつもりだとのこと。今後の動きが気になるところです。
|