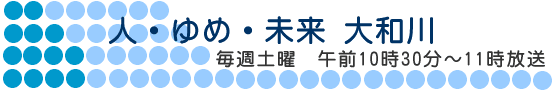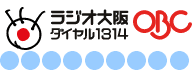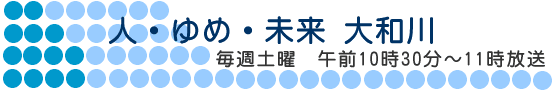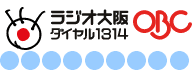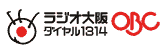| ムカシトンボがすめる川
谷さんは大和川のイベントでいつも大活躍。今回も水生生物調査の講師をされる予定でした。
谷 川の中にいる生き物を調べると、「きれいな水」「少し汚れた水」「汚れた水」「大変汚れた水」の各水にすむ生き物がいて、それで水の状態が判断できます。飛鳥川には、サワガニ、ゲンジボタルが食べるカワニナ、コヤマトンボ、オニヤンマ、コオニヤンマ、トノサマガエル、ツチガエルなどがたくさんいます。水質は「きれいな水」から「少し汚れた水」ぐらいの範囲で、あえて言うなら「きれいな水」です。
特に注目すべき生き物は何でしょう。
谷 上流にいるムカシトンボです。そのヤゴ(幼虫)は15℃の水で7年間生きるため、7年生のヤゴが見つかったら、過去7年間はそこに15℃の「きれいな水」が流れている保証になります。もう一つは川底にいるヒゲナガカワトビケラで、口から出した糸で石をつづって巣を作ります。これがいれば川底が安定していることが分かります。砂だと川底が動いてと安定しません。飛鳥川では、石にケイソウという藻があり、それをアユが食べます。
以前から、この美しさを保てているのでしょうか。
谷 この上流部に限っては、美しさは維持されていますが、町の中になると汚水が入っています。特に最近は、家庭排水がよく流れています。
大和川全般に目を転じると、昨年も全国の一級水系で水質ワースト1となりました。
谷 40年ほど前はBOD(生物化学的酸素要求量)が30mg/リットルという、し尿がそのまま流れているような汚れ方でした。今はアユがすめると言われている5mg/リットル以下で、現に2年ほど前から下流域でもアユが自然の状態で産卵し、暮らしています。改善率はすごいのですが、奇麗な川もさらに奇麗になったため、全国的にはワースト1のままです。40年ほど前までは高度成長期で公害問題が起き、工場からの汚水で水質が悪化しました。一方、竜田川が今とても汚れているのは、人口増加による家庭排水が主原因で、浄化センターも造っていますがオーバーするからです。
やはり流す方の意識が大切なようです。
谷 そのためにも今日のようなリバーウオッチングを通じ、家族、特に若い保護者にも来てもらって、川を奇麗にする意識を持ってもらいたいと思います。
|
誰でもできる家庭排水対策
ここでキッズ
リポーターたちから質問が出ました。
永井 どんな生き物がいたら水は奇麗なんですか。
谷 サワガニやカジカガエル、アマゴなどがいたら「きれいな水」ですね。カワニナやマシジミ、コヤマトンボ、オニヤンマなどは「少し汚れた水」。シオカラトンボなどが出てきたら「汚れた水」です。「大変汚れた水」であればユスリカ。そういう所は、わずかな種類の生き物しかおらず、その個体数が大変多いんです。
健人 大和川にはどんな昆虫がいるんですか。
谷 飛鳥川の上流だとムカシトンボ。オニヤンマやアメンボ、コヤマトンボもいます。
翔太 水の中にはどんな生き物がいるんですか。
谷 「きれいな水」にはアユやアマゴ、「少し汚れた水」ならカワムツやオイカワ。「汚れた水には」フナ、「大変汚れた水には」ウシガエルなどがいます。
大和川をこれからも良くするためには、どんなことが必要なのでしょう。
谷 一つは下水道完備といったハードの面です。一方、家庭排水に気を付けるソフト面も大切です。食べ物を残さない、食器の汚れをできるだけ拭き取る、アクリルタワシを使う、洗剤など濃い液体を使わないといったことです。濃い洗剤や毒のある物を使うと、汚れを分解する微生物が死んでしまいます。せっかく立派な下水処理場を造ってもだめ。一人一人が家庭から考えていくことが一番大切なんですね。
健人 お母さんは洗濯で洗剤を少なめに使っています。
翔太 食器洗いではアクリルタワシを使っています。
小出君兄弟は、普段から気を付けているお母さんの姿をよく見ていました。
******

豊かな自然の中を
流れる飛鳥川
|
永井 水が底まで透き通って入りたかったけど、中止なので今度来た時に入りたい。
健人 ゲンジボタルの幼虫が1匹でカワニナを24匹ぐらい食べると聞いて、びっくりしました。
翔太 谷先生にいろんな虫を教えてもらえて、うれしかったです。
イベントは中止になりましたが、3人には色々な発見や驚きがあったようです。 |