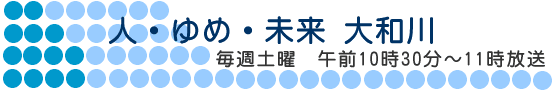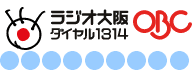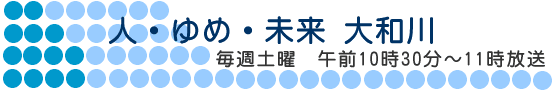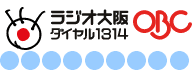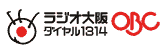| 杭で造る瀬と淵
畝傍中学校を訪ね、科学部顧問の松本清二先生に、社会実験でどんなことをするのかを伺いました。
松本 校区を流れている飛鳥川の水を3日に分けて取り、BODやCOD、にごり具合などを調べます。実験前、実験期間中、実験最終日の3日、それぞれ夜7時、8時、9時に水を取り、奈良県保健環境研究センターで分析をしてもらいます。
飛鳥川の環境改善への取り組みについても伺いました。なぜ始めたのでしょう。
松本 2001年ぐらいから、飛鳥川を使って環境学習の授業をしていましたが、たまってきた土砂の浚渫(しゅんせつ)工事が行われたため、生き物や土が取りさらわれて“水路”になってしまいました。名勝指定されている大和三山の中を流れている川だし、地域住民も蛍の保護に取り組んでいましたので、(蛍の餌となる)カワニナや、魚、鳥が戻ってくる川にしたいと思ったのがきっかけです。
環境改善のための杭打ちについて、部長の楠部仁章君と副部長の小泉智裕君に聞きました。
楠部 両側がコンクリート二面張の水路のような川で、水量も少ないため、その中に蛇行した細い川をもう1本造ればコンスタントに水が流れるだろうと考えました。杭を打つことで、瀬と淵を造って生き物がすみやすくし、川の下に流れている伏流水が上がってきて水量が増える効果を期待しています。去年だけで250本を打ち込みました。
小泉 今では中州などが出来て、色々な動物が戻ってきています。去年の夏にはカモの巣も見つかり、ドンコやオイカワなどの魚も来るようになりました。
生活排水を出さない努力について、部長と副部長、部員の高羽祐馬君と土田稔久君に聞きました。
楠部 飲み物などを直接流さないようにしています。
高羽 使った油をキッチンペーパーで拭いています。
土田 米のとぎ汁を花にあげたりしています。
小泉 僕も米のとぎ汁を花にあげたりしています。

左上から、高羽君、土田君、
小泉君、楠部君
下が松本先生
|
|
廃油を回収して石けん作り
大和川流域生活排水対策社会実験まで、あと1週間。橿原市役所を訪れ、環境対策課の加藤智治(としはる)さんにお話を伺いました。
加藤 約3年前から飛鳥川の草刈りや清掃作業をするなど、飛鳥川の環境に関心をお持ちの地元自治会にお願いをし、今回の社会実験に取り組みます。この社会実験にあわせ、2月13日から15日まで、万葉ホール1階多目的ロビーで環境啓発パネル展を開催します。地球温暖化と身近な河川の環境が、私たちの暮らしと大きく関わっていることを考えていただく内容です。また、16日には、イオンモール橿原アルル1階ロビンコートでも、同じパネル展と、生活排水対策について紙芝居を用いて解説する大和川博士講座を行います。
橿原市では、日ごろから飛鳥川流域の他の市町村と一緒に行っていることがあります。
加藤 川西町、三宅町、田原本町、明日香村と「飛鳥川流域生活排水対策推進会議」を形成し、河川汚濁原因の8割と言われる家庭からの生活排水を流さない工夫を地域住民に呼びかけています。とくに、最大原因の使用済み食用油は、平成7年度より回収を行っていて、それでリサイクル石けんを作り、回収時、油と引き換えにお渡ししています。回収量は年々増え、昨年度は5市町村で約1万2500リットル集まりました。
 加藤さんと
加藤さんと
|
橿原市単独での取り組みも行われています。
加藤 話し上手な若い職員が、希望する市内の小学校4年生を対象に、生活排水対策に関する出前授業を平成13年度より行っています。水の大切さや河川汚濁とその対策について講義し、パックテストで河川水質の簡易検査を行います。食用油などを直接流さないといったことを授業で学び、それを家庭で実践することで、子から親へ逆に伝えられます。小さい時に学んだことは、大人になっても意識の片隅に残りますので、これを続けることで将来的に河川水質がよくなるとも考えております。飛鳥川に万葉の清流が復活し、子供たちが水遊びのできる川になれたらと思っています。
******
杭を打ち込んだり水質調査をしたりと、飛鳥川の環境のために取り組む畝傍中学校の皆さん。廃油から石けんを作るなど、色々な工夫をして生活排水を減らす取り組みをする方々。多くの人々が、さまざまな方向から川を奇麗にしようとしていることを知ると、自分もますます頑張れるような気がしました。
|