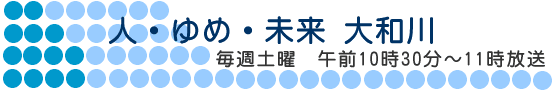
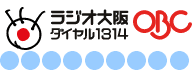
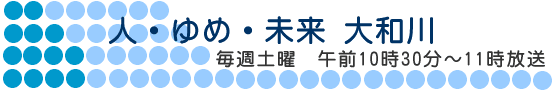 |
|
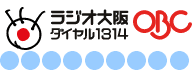 |
清酒発祥の地、菩提仙川 奈良市南東部の谷筋、市内屈指の紅葉の名所である正暦寺。そこに流れる菩提仙川は、大和郡山市内で佐保川に合流する大和川水系の川で、生い茂るカエデやモミジなどの木々や正暦寺の建物と一体となり、美しい山の風景をつくり出しています。川沿いには「日本清酒発祥之地」と刻まれた石碑が建ち、毎年、正暦寺で「菩提もと清酒祭」が行われます。清酒祭を訪ね、大和川とお酒の関係を探りました。 |
| 寺と酒の「意外な」関係 菩提もと清酒祭が始ると、川のせせらぎと鳥の声以外には何も聞こえない正暦寺本堂に、お経が響きました。参加者の中には、清酒業界の関係者かと思われる人々も。これが終わると、本堂から少し下った菩提仙川沿いの庭で、尺八や和太鼓の演奏、餅つきやかす汁の振る舞いなども行われました。そんな中でお話を伺ったのは、大原弘信(こうしん)住職です。 「日本清酒発祥之地」の石碑がありました。 奈良県菩提もとによる清酒製造研究会のメンバーお二人、奈良市の八木酒造・八木威樹社長と、御所市の油長(ゆうちょう)酒造・山本長兵衛社長にも伺いました。大正時代に途絶えた菩提もとによる酒造復活は、どのように始まったのでしょうか。
|
大切なのは水風景を守ること 山本さんは、酒造の歴史にも精通されています。 なぜ、正暦寺はお酒造りに向いていたのでしょう。 再び大原住職に伺いました。今も菩提仙川の水を使って、菩提もとを造っているのでしょうか。 それは、大和川の河口まで流れている水でもあります。上流を預かる立場としての思いを伺いました。 お話を伺った後、菩提仙川沿いを正暦寺本堂よりもさらに奥へと歩きました。川に目をやると、石にこけが生え、魚が泳いでいるのがはっきりと見えます。かなり水が奇麗です。そして、大きめの石で出来た階段状になったところを上がり、橋の近くまで行くと、なんと滝が現れました。自分は大自然のど真ん中に立っているんだなという、不思議な気持ちになれます。 ******
10月21日、奈良市の正暦寺で行われた菩提もと清酒祭を訪ねました。一度途絶えたものを復活させるのは、本当に大変なこと。やり遂げた皆さんの熱意を感じました。そして、お酒造りを通し、豊かな自然や文化が伝わっていけばいいと思います。皆さんも、大和川でその歴史に思いを馳せてはいかがでしょうか。 |
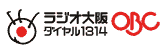 |