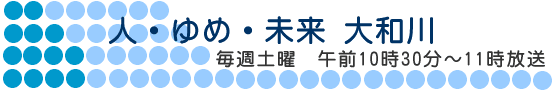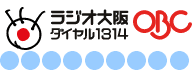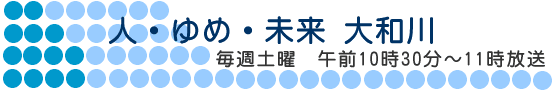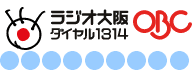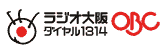| 殿様が伝えた最先端の趣味
近鉄郡山駅から徒歩10分、金魚の養殖、卸売、小売の「やまと錦魚園」には、「郡山金魚資料館」があって無料公開されています。やまと錦魚園代表で郡山金魚資料館の館長、嶋田輝也さんにお話を伺いました。まずは、年間の生産量から。
嶋田 500〜600万匹は出荷しています。江戸の元禄時代から養殖が始まった郡山全体では、全国2位の約7千万匹を出荷、養殖業者は約70軒です。金魚は千年ぐらい前に中国で見つかった赤いフナが元祖と言われ、それが約400年前に堺の港に伝わったものの、戦国時代で金魚どころではなく、日本には定着しませんでした。大和郡山には、柳沢吉里公が甲斐国から来て郡山の殿様になった時、趣味で飼っている金魚を持ってきたと言われています。当時、金魚は江戸文化において、一番トレンディーなお金持ちの趣味やったということです。
養殖がここまで盛んになった理由は?
嶋田 大和川水系である生駒山の伏流水が、金魚に合っていたとよく言われます。特にこの地域は水に恵まれています。ただ、いつでも金魚があるように思われがちですが、出荷後で全然ない時もあります。そこで、いつ見学に来られても魚がいるようにと、2代目の父が資料館を造りました。日本の金魚のほとんどを展示していて、変わったものでは、青森県の津軽錦、高知県の土佐錦(きん)、島根県の出雲ナンキンなどもいます。また、金魚博士と言われた松井佳一先生が集められたものを基に、金魚に関する書物や金魚が描いてある浮世絵のコピーなどの資料も置いています。
小さな金魚すくいの金魚から、グレードの高い金魚まで、色々そろっています。値段は、いくらぐらいするのでしょうか。
 郡山金魚資料館
郡山金魚資料館 |
嶋田 安い値段のものから置いているけど、一番高くて、50万円ぐらいの金魚が売れる時もあります。常時置いておくのは大変だから、こんなの欲しいって注文聞いてから、用意するんですけどね。 |
金魚と富雄川と佐保川の関係
金魚の養殖は、どのような手順でするのでしょう。
嶋田 まず、秋に親選びをします。琉金(りゅうきん)やランチュウなどは形のいいものを、金魚すくいのはできるだけ赤い親を使います。冬に吉野の方から水草を取ってきて、それに採卵した卵を付けます。産卵は4月中旬ごろ始まり、大きな金魚は1回に3千粒ぐらい産んで、9割近くがかえりますが、商品になるのは、琉金で4割、ランチュウだと1割ぐらいです。
出荷できる金魚の基準などはあるのでしょうか。
嶋田 サイズもある程度決まっていますが、やっぱり色。金魚はみんなフナみたいな色から赤くなっていきますが、色の上がりのいいものから売ります。同じ郡山でも、少し離れた養殖場とこの周辺では、色が違ったりします。植物プランクトンを繁殖させるんですが、土によってその種類が違うのではと思っています。
どこから水を引いているのでしょう。
嶋田 富雄川やね。高低差があって水の引きが早いから、排水は全部佐保川です。
大和郡山市では、「全国金魚すくい選手権大会」が毎年行われます。
嶋田 金魚の町で一大イベントをやろうと、業界と大和郡山市が頭を絞って考えました。今、一番困っているのは、すくった金魚を持って帰ってくれないこと。お母さんが、「そんなん持って帰ったら…」って言う。だから、金魚が売れないんです。
金魚を買う場合のポイントも伺いました。
嶋田 元気に泳ぎ回り、少しふっくらしている金魚がいい。品種を決め、事前に勉強して、その品種の特徴がよく出ているものを買います。人気のピンポンパーやランチュウは、循環ろ過しない方がよく、そうした水槽の器具などもちゃんと調べて、いい環境作ってやらないと。水槽には、金魚の糞などを奇麗にしてくれるバクテリアがいますが、金魚を入れるまでにそのバクテリアを作りたい。水を替える時にも、洗いすぎずに、ある程度バクテリアを残してあげるようにします。
******

嶋田さんと |
大和郡山市でお話を伺い、身近なのに意外と知らなかった金魚の歴史や、人間との関わりが、とてもよく分かりました。その金魚を育てているのは、大和川の支流である富雄川の水。人間はもちろん、生物というのは、自然から色々なものをもらい、お世話になっているのだなあと感じました。
|