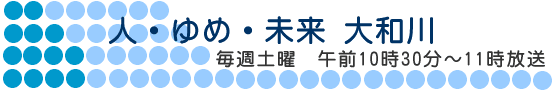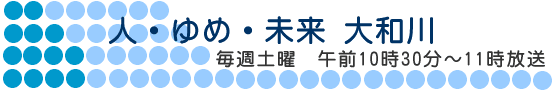| 冷たくて熱い修行
千光寺から急斜面を下り、高木がうっそうと茂る滝へと出ました。ほら貝の音と共に始まった滝行では、般若心経(はんにゃしんぎょう)を唱え、一人ずつ滝に打たれます。水はとても冷たそうです。
滝行を終え、一休みされている女性に伺いました。水の冷たさや衝撃はどうなのでしょう。
女性 滝に当たっている間は全然分かりません。自分の辛いことなどを念じていると、全く分からないんですね。入る時と出た後の水の冷たさだけが残っていますね。滝行は体調が悪かった時に薦められて始め、今度で5回目ぐらい。足の具合が悪く、普通はあの坂は歩けないんですけど、お滝の日やお寺の行事の日はすごく早く歩け、山、土地、水の力を感じます。
この水の行き先である大和川のイメージは?
女性 つい何年か前までは汚い川でしたよね。でも、最近はちょっと奇麗になったんじゃないですかね。
 火渡り修行
火渡り修行 |
一休みの後、ほら貝を先頭に全員が再び滝のところまで行き、今度は当たるのではなく、横の磨崖仏に向かってお勤めを行いました。それが終わると、千光寺の境内では火が焚かれ始めました。ヒノキの葉を集めて作った「柴灯護摩(さいとうごま)壇」に火が着けられ、白い煙がもくもくとわき出し、その煙が黄色がかり、さらに茶色くなってくると、ようやく炎が見え、熱を感じはじめます。やがて護摩の火は小さくなって「おき火」となり、護摩壇を組んでいた熱された丸太が地面に敷かれて、その上を素足で渡る「火渡りの行」が始まりました。渡られた方に、お話を伺いました。
女性 熱くなかった。初めはちょっと恐かったんですけど、渡ろうと思った瞬間に渡ったら、全然熱くなくって。熱気みたいなものが、わっと下からわいてきて、体全体が下から熱くなるような感じはありましたが、なにかご加護を受けたみたいな気がしました。
渡る前後で、気持ちの変化はありましたか?
女性 気持ちがすっきりしたというか。嫌なことを忘れた感じがします。
|
煩悩を水で洗い流し
火で焼き尽くす
終了後、千光寺の住職、大塚静遍(じょうへん)さんにお話を伺いました。まずは、千光寺の歴史から。
住職 680年ごろに役行者(えんのぎょうじゃ)という方が、ここで10年ほど修行された後、大峯山山上ケ獄へと登られました。そのため、ここは「元山上」と呼ばれています。千光寺の名は、後の天武天皇の時代に頂きました。
普段から、滝行はよく行われているのでしょうか。
住職 滝行は一般的になっており、最近は女性が大変増えています。また、修験者より一般の方が多いのではと思います。ストレスが多いので、滝に打たれて身も心も清める意味や、自分の弱い面を強くしようという気持ちもあるのではと思います。ことに女性は。
滝まつり火渡り修行の意味を伺いました。
住職 滝のぐるりの仏様を供養する意味もありますが、最近は、暑い夏を無事に過ごせるよう、厄よけや、身も心も清めるという意味があるんじゃないかと思います。欲や煩悩や悩みといったものを、水で洗い流し、火で焼き尽くすことで、心身共に奇麗にさわやかになるということじゃないかと思います。
役行者がこの地を選んだのは、なぜでしょう。
住職 一番は水が奇麗であること。それと、大木がたくさん茂り静かな場所であること。もう一つは、都に近いということ。役行者さんをお祭りしてある所には、弁天さんを祭っている所が多いんですよ。弁天さんは水の神様なので、行者さんは水をすごく大切にされ、私たちの生活に水が必要であることを痛感されていたのではないかと思います。山の木や土には水が含まれ、そこから奇麗になった水だけが流れてきます。昔から山を尊んできたのは、奇麗な水を出してくれる所であり、神様の宿る所としてきたからです。川を奇麗にするということは、山を奇麗にするということにつながるのではないかと思います。今は山を奇麗にすることが、忘れられているんちゃうかな。
******
 大塚住職と
大塚住職と |
滝と火は、対照的なものであるものの、どちらも神秘的で、修行を終えた皆さんが「心が無になった」「すっきりした」と口をそろえていたのが印象的でした。私たちは、昔から自然のパワーを支えにして生きてきたんですよね。皆さんも、色々な形で、自然、そして、大和川に触れてみてください。
|