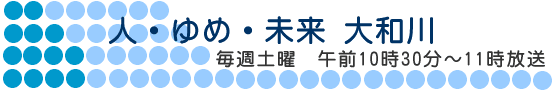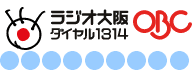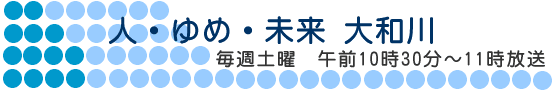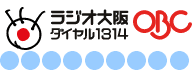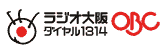|
バランスのとれた風景は
豊かな生命力がある証し
皆さんが目指している「飛鳥川の原風景」というのは?
水谷 会の設立時に討議した中で、栢森地区総代を25年間務めた現会長の少年時代の風景、つまり昭和初期の風景を取り戻そうということになりました。
今見えている風景も、昔ながらの素晴らしい農村の風景だと思うんですが、やはり違うのでしょうか。
水谷 ご覧のように、緑色の山が川の近くまで迫っています。戦後、国の拡大造林政策で、棚田にもスギやヒノキを植えたため、明日香村の山は94%が人工林になりました。雨が降った時、広葉樹の山があれば、落ち葉などが水を吸収しますが、スギやヒノキだけでは、山の持つ保水力が非常に低く、土砂が川へ一気に流れ込みます。子供や孫たちに残したい原風景というのは、棚田や川があり、川の周りには四季折々の草花が咲き、秋に色付く広葉樹の山があって、遠くにスギやヒノキの青山がある、という風景なんです。
なるほど。木が多いだけで自然が豊かだと思っていましたが、本来のあるべき姿ではないのですね。
*
栢森集落の入り口から5分程上流に歩いてきました。
水谷 ここが飛鳥川と名前の付く最初の地点です。山から流れる寺谷川と畑谷川がここで一つに合流して、飛鳥川となります。ここから橿原市、三宅町を通り川西町で大和川につながります。この辺りは万葉集にも詠まれるなど、物流の手段というより、非常に人に親しまれてきた川というのが特徴です。
畑谷川に沿って上流へ行くと、集落に入りました。民家の横にも小川が流れています。人々が川と一緒に生活しているんですね。そして、神社が見えてきました。
水谷 加夜奈留美命(かやなるみのみこと)神社です。学者の方が、ここの石碑に「おかみ」という水源の神様を表す字を発見されました。また、川の向こうにあるのが南淵山です。日本書紀には、天武天皇5年の時に、この山の伐採禁止令が出たとあります。古来から下流域の人々の生活を守る水源の森として、非常に大切にされてきた山なんです。しかし、その山が今は、荒れてしまっている。そのことに心を痛めたことが、私たちの活動のきっかけとなっています。
*
畑谷川をどんどん上がり、女淵(めぶち)の滝に到達しました。透き通った川が間近に見えて素晴らしいです。
水谷 ここで皇極天皇が雨ごいをされたという伝説があります。以前は、ここまで来ることもできない程荒れていたので、私たちの手で木を切り、川から石を集め、間に砂を入れて踏みしめるという方法で、自然の落差を利用した70mほどの道を造りました。
|
川と人との距離が
川の美しさを左右する
木を減らすほか、植樹もされたんですか。
水谷 はい。ただ、私たちの活動は、元あった草木が元気を取り戻すお手伝いをするというのが主眼です。スギやヒノキを切ってもいい所は広葉樹に変えていこうと、少しずつ取り組んでいます。今年は国蝶のオオムラサキを戻すために、サナギから次世代の卵を得るまでの小屋を間伐材で造ったり、オオムラサキの餌となるエノキの木を活用して、おいしいヒラタケを植菌したりしました。また、間伐材のクヌギをコースター状にしたエコマネーを作り、活動の参加者の方に渡しています。エコマネーは、地元の野菜やお米などと交換できるようになっています。
下流の大和川については何か感じられますか?
水谷 橿原市など中流域がまだ汚れていると思います。大きな原因はコンクリートの護岸工事かと。これは人と川とを遠ざけていると思います。単に水路の役目しか果たさない川は、下水が完備されても美しくなるのは遅れる。また、雑草が茂っても、川に近付くことができない。昔は、人による手入れが地域でできていましたが、今は崩れてます。だから、なるべく川と人とが近付けるような工事、川との接し方が大切だと思います。
******

水谷道子さん(右)と
|
今回は素晴らしい飛鳥川の様子をご案内頂き、とても癒されました!しかも、山小屋のいろり端でお話を伺っている時、きなこ団子を出して頂いたんですが、四方八方を大きな山に囲まれた田園風景の中で食べるきなこ団子の味は最高においしくて、本当に気持ちいいひとときを過ごすことができました。
|